道路交通法違反事件の弁護活動
刑事事件・少年事件Contents
道路交通法違反事件の弁護活動
はじめに
本コラムでは、道路交通法違反事件の弁護活動について、淡路島の弁護士が解説いたします。
道路交通法は、違反と結果の程度に応じて、10年以下の懲役から科料まで幅広い刑罰を定めています。
「速度違反」の法定刑は、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
「無免許運転」の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
「酒気帯び運転」の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
「酒酔い運転」の法定刑は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
「救護措置義務違反(いわゆるひき逃げ)」の法定刑は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
各違反ごとの量刑相場などは以下のとおりです。
逮捕・勾留、保釈について
道路交通法違反事件では、逮捕されて、同種前科があって公判請求後に実刑が予想されるケースであっても、勾留されず、在宅捜査となることが多いです。
もっとも、身元が確認できない場合など逮捕されてしまうことがあります。
起訴後勾留されてしまっている場合でも、保釈請求すれば認められる可能性は高いです。
起訴された場合の量刑相場
1 「速度違反」の量刑相場
「速度違反」では、以下のとおり、ほぼ制限速度超過の程度に応じて形式的に刑が決められています(ただし、高速道路の方が一般道路よりもやや軽い量刑になっています)。
時速30キロメートル未満(高速道路では時速40キロメートル未満)の超過では、交通反則通告制度により処理されます。
時速30キロメートル以上(高速道路では時速40キロメートル以上)、時速80キロメートル未満の超過では、略式請求による罰金刑が科されることが多いです。
時速80キロメートル以上の超過では、公判請求による執行猶予付きの懲役刑が科されることが一般的です。
ただし、短期間での同種再犯の場合や、執行猶予期間中の再犯の場合では実刑に処せられることになります。
2 「無免許運転」の量刑相場
「無免許運転」は、交通反則通告制度の対象外であることから、道路交通法違反事件の中で、刑事責任を問われる可能性が高い違反類型です。
「無免許運転」では、同種前科の有無・程度により刑が決定することになります。
初犯では略式請求による罰金刑になることが一般的ですが、「無免許運転」を繰り返し行った場合には、執行猶予付きの懲役刑に科されることになり、前刑執行猶予期間中の再犯では実刑となります。
「無免許運転」では、本件に至るまでの経緯全般を反省し、再案防止に向けて自動車の運転をしない生活環境の整備が重要になります。
通勤や業務において自動車を使用していた場合、家族、就労先の理解・協力によって、生活環境を整備する必要がありますし、被疑者・被告人名義の自動車については、処分した上で、処分したことを証する書類などを検察官・裁判所に提出することを準備します。
3 「酒気帯び運転」の量刑相場
「酒気帯び運転」とは、身体に保有するアルコールの程度が血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつきアルコール0.15ミリグラム以上の場合をいいます。
「酒気帯び運転」では、初犯は略式請求による罰金刑になることが多いものの、近年の厳罰化傾向から公判請求による執行猶予付きの懲役刑となる事例もみられるようになってきています。
「酒気帯び運転」のうち、呼気1リットルにつきアルコール0.25ミリグラム以上の場合は、行政上の違反点数が25点となり、免許取り消し処分(欠格期間2年)になることが見込まれ、「無免許運転」と同様に自動車の運転をしない生活環境の整備が必要になります(なお、同0.25ミリグラム未満の場合、免許停止(90日間)となることが見込まれます。)。
4 「酒酔い運転」の量刑相場
「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいい、「酒気帯び運転」とは異なり、アルコールの数値に関係なくアルコールの影響で正常な運転ができない場合に対象となります。
「酒酔い運転」では、ほとんどの場合で罰金刑にとどまることなく、公判請求による執行猶予付き懲役刑になります。
前刑の執行猶予中などの場合、実刑になり、刑期も「酒気帯び運転」よりも長くなります。
「酒酔い運転」では、行政上の違反点数が35点となり、免許取り消し処分(欠格期間3年)になることが見込まれ、自動車の運転をしない生活環境の整備が必要になります。
5 「救護措置義務違反(いわゆるひき逃げ)」の量刑相場
「救護措置義務違反(いわゆるひき逃げ)」では、交通事故によって被害者が生じていること、すなわち、過失運転致死傷罪が成立していることが前提となります。
過失運転致死傷罪(人身事故)の弁護活動に関しては、こちらをご参照ください。
「救護措置義務違反(いわゆるひき逃げ)」では、逃亡又は罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれありとして、逮捕・勾留される可能性が高いです。
「救護措置義務違反(いわゆるひき逃げ)」は、過失運転致死傷罪の量刑を重くする要素となり、逃走した理由、逃走していた時間や距離などの犯情の重さは、量刑の幅にも影響を及ぼします。
なお、「救護措置義務違反(いわゆるひき逃げ)」の法定刑は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金であるため、過失運転致死傷罪の法定刑(7年以下の懲役・禁固又は100万円以下の罰金)よりも重いです。
また「救護措置義務違反(いわゆるひき逃げ)」では、行政上の違反点数が35点となり、免許取り消し処分(欠格期間3年)になることが見込まれ、自動車の運転をしない生活環境の整備が必要になります。
刑事事件・少年事件の弁護士費用
捜査弁護活動(起訴前弁護活動)
(着手金)
(報酬金)
公判弁護(起訴後弁護)
(着手金)
(報酬金)
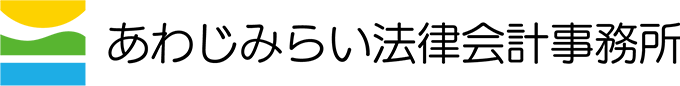
 24時間365日受付
24時間365日受付