著作権について
企業法務Contents
著作権
はじめに
本コラムでは、著作権について、淡路島の弁護士が解説いたします。
1 著作権の保護範囲
1 原則
原則として、他人の著作物を利用する場合には、著作物の著作権者の許諾を得る必要があります。
2 例外
以下の場合、著作権者の許諾を得ることなく著作物を利用することができます。
1 条約加盟国以外の外国人の著作物
日本が加盟している条約加盟国民の著作物などは、日本においても著作物として保護されることになります。
これによって、世界の大半の国の著作物が保護されることになり、著作権には国境がないということができます。
もっとも、エチオピアやイランなどの国と日本との間には条約関係がありません。
したがって、これらの国の著作物は保護の対象になりません。
2 憲法・その他法令、告示・訓令等、判決・決定等
憲法・その他法令、告示・訓令等、判決・決定等は、広く国民の利用に供する必要があることから、著作権は否定されています。
3 著作権者の死後70年が経過した著作物
著作権の保護期間は、著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後70年までです。
なお、著作権の保護期間は、2018年、死後50年から死後70年に延長されました。
4 権利制限規定による例外
著作権法では、一定の場合に著作権を制限して著作物を自由に利用することができることとしています。
具体的には、著作権法第30条から第47条の6までに定められており、以下のとおりです。
・私的使用のための複製(個人又は家族等で利用するための複製)
・付随対象著作物の利用(いわゆる「写り込み」の対象となる他の著作物の複製又は翻案)
・図書館等における複製
・引用(引用の目的上正当な範囲での引用)
・教育用図書等への掲載・複製等、視覚・聴覚障がい者等のための複製
・営利を目的としない上演等
・時事問題に関する論説の転載等、政治上の演説等の利用、報道のための利用
・裁判手続等における複製
・行政機関情報公開法等による開示、公文書管理法による保存等のための利用
・放送事業者等による一時的固定
・一定の美術に関する展示、利用、複製等
・プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等
・電子計算機における著作物の利用に付随する利用等、電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等
・翻訳、翻案等による利用
2 著作権者
1 原則
契約書などで取り決めも行わなかったという場合、原則どおり、著作権は著作者(クリエイター)に帰属します。
なお、契約とは当事者の合意・約束のことをいいますので、契約書などの文書がなくても、口頭やメールでも契約は成立し得るので、著作者(クリエイター)としては、意図せず著作権を譲渡していることのないよう、留意する必要があります。
例えば、クライアントが著作者(クリエイター)に提出した見積書において、料金が著作権譲渡の対価であることを明記され、クリエイターにおいては何らの異議を唱えることがなかった場合には、契約書がなくとも著作権のクライアントへの譲渡が認められる可能性が高いと考えられます。
裁判例においては、モデルのファッション撮影の電子データについて、写真家が「どのように使うかは御社次第です」などとメールしていた事案において、著作権の譲渡までは認めなかったものの、「宣伝目的であればトリミングなどは使用者に任せるという包括的な許諾をしていた」と判断し、著作権の侵害を認めませんでした(東京地判平成27年11月20日)。
2 例外
原則として、著作権(及び著作者人格権)は、著作者(クリエイター)に帰属しますが、著作権は譲渡することもできます。
著作者(クリエイター)がクライアントに成果物を納品する場合、以下のとおり、著作者(クリエイター)及びクライアント間では、著作権(及び著作者人格権)について契約書等において明確に取り決めを行っておくべきです。
これによって、著作権者の許諾を得ることなく著作物を利用することができます。
1 著作権の譲渡
契約内容や料金次第で、著作権は著作者(クリエイター)からクライアントに譲渡されることになる場合があります。
例えば、企業のロゴや商品のパッケージデザイン等の長期間使用することを想定した成果物では、クライアントとしては著作権の譲渡を受けておくべきです。
また、キャラクターのデザインでは、ウェブサイトに使用したり、グッズ化等の商用利用が想定されることから、同じくクライアントとしては著作権の譲渡を受けておくべきです。
一方で、クリエイター側では、著作権を譲渡する場合でも、成果物を自身のポートフォリオとして作品を公開することができるよう、「媒体を問わず、成果物を自己のポートフォリオとして公表することができる」などの条項を設けることをおすすめします。
2 著作者人格権の取扱い
著作者人格権は、著作権とは別個独立の権利であり、著作権を譲渡した場合であっても、著作者は一身専属権として著作者人格権を行使することができます。
また、著作者人格権はそもそも一身専属権であるため、譲渡自体できません。
ただし、実際の取引においては、上記「2」のように著作権を譲渡する場合、併せて「著作者人格権は行使しない」という取り決めがなされることが通常です。
3 職務著作
1 職務著作とは
職務著作とは、従業員が業務上、法人名義での公表が予定される著作物を創作した場合、法人に著作権及び著作者人格権を帰属させる制度をいいます。
著作権(及び著作者人格権)は、原則として、著作者(クリエイター)に帰属しますが、職務著作に該当する場合、例外として、法人に著作権及び著作者人格権が帰属します。
このため、従業員が在職中に創作した著作物についてはもちろんのこと、フリーランスとして創作した著作物であっても勤務形態などによっては、著作権及び著作者人格権が法人等に帰属することが考えられます。
このような場合、従業員・フリーランスとしては、退職後・取引終了後等に創作した著作物を使用する場合には、法人等の承諾を得なければならないことが考えられるます。
したがって、あらかじめ雇用契約書・業務委託契約書等に著作権及び著作者人格権の取り決めを行う等しておくことをおすすめします。
2 職務著作の要件
以下の場合、著作権者の許諾を得ることなく著作物を利用することができます。
1 法人等の発意に基づき、業務に従事する者が職務上作成すること
法人等の発意に基づきの要件は、著作物の創作をすることの意思決定を法人が行っていることであり、会社からの具体的な指示、命令がなくても、雇用関係にある従業員が創作をしていれば、通常該当します。
また、業務に従事する者が職務上作成するの要件は、従業員のみならず、業務委託、請負等の場合でも、会社の指揮監督の下で創作している場合は該当します。日本においても著作物として保護されることになります。
2 法人等の名義の下に公表すること
法人等の名義の下に公表するという要件は、法人等の名義で実際に公表されたもの、及び、公表が予定されていることをいいます。
また、裁判例においては「公表を予定していない著作物であっても、仮に公表するとすれば法人等の名義で公表されるべきもの」も含まれると判示されています(知財高判平成18年12月26日)。
なお、プログラムの著作物には、公表を予定されていないものが存在することから本要件は不要とされています。
3 別段の定めがないこと
雇用契約、就業規則・社内規程等において、従業員が著作権及び著作者人格権を有するという定めがなされている場合、当該規定に従って、著作権及び著作者人格権は従業員に帰属することになります。
ただし、このような規定が存在することは実務上稀であると考えられます。
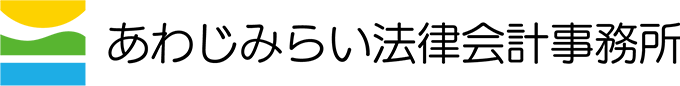
 24時間365日受付
24時間365日受付