生前贈与について
遺言 相続生前贈与
はじめに
相続税の節税対策などの生前対策として、もっとも取り組みやすいのが生前贈与です。
ただし、一口に生前贈与といっても、贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税があり、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で制度選択なくしては、有効に生前対策を行うことはできません。
生前贈与に関しては令和5年(2023年)税改正において、相続時精算課税制度、暦年課税制度いずれも税制改正が行われており、新たに生前贈与を考える場合、既に生前贈与を行っている場合でも、相続時精算課税・暦年課税のいずれを選択するのかを(再度)検討する必要があります。
そこで、本コラムでは、生前贈与について、淡路島の弁護士が解説いたします。
実務上、相続税の税務調査などにおいては、贈与財産か名義財産かについて、事実認定の問題が生じることが良くあります。
こうした制度選択・事実認定の問題は専門的なものとなることが考えられますので、まずは(相続実務に精通した)弁護士・税理士に相談することをおすすめします。
贈与税の仕組み
贈与税の課税方法には、➀暦年課税と➁相続時精算課税があります。
そして、受贈者(贈与を受けた者)は、贈与者(贈与をした者)ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。
贈与税の申告と納税は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までにする必要があります。
また、贈与により土地や建物を取得した場合、贈与税とは別に不動産取得税を納める必要があります。
1 ➀暦年課税
➀暦年課税とは、1年間に贈与を受けた財産の合計額をもとに贈与額を計算する方法です。
贈与税の暦年課税は、暦年ごとの贈与額(1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の価額の合計)から基礎控除110万円を控除した上で、累進課税率を適用して計算します。
なお、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭(特定贈与財産)の贈与では、2000万円を控除した上で、累進課税を適用して計算します。
また、贈与者の相続時には、死亡前3年以内(2024年(令和6年)1月1日以降の贈与では死亡前7年以内、ただし、延長した4年間に受けた贈与のうち100万円までは相続財産に加算しない。)の贈与額を贈与者の相続財産に加算して相続税を課税しますが、特定贈与財産では、贈与額を相続財産に加算しません。
2 ②相続時精算課税制度
②相続時精算課税制度とは、贈与を受けたときに、特別控除額及び一定の税率で贈与税を計算し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算する方法です。
具体的には、60歳以上の両親(祖父母)から18歳以上の子ども(孫)に贈与をした場合、累積贈与税額2500万円までは課税されず、2500万円を超えた部分は20%の税率で課税されます。
そして、相続時精算課税制度を選択した後に、暦年課税制度に戻ることはできません。
相続時精算課税制度により贈与した特定贈与者の相続時には、この制度を利用して累積した贈与額を相続財産に加算して相続税を課税します。
なお、2024年(令和6年)1月1日以後の贈与に関しては、相続時精算課税制度においても、上記の2500万円の控除とは別途、基礎控除110万円を控除できることになりました。
贈与税の非課税措置
1 生活費・教育費(通常必要と認められるもの)の非課税
扶養義務者相互間における生活費又は教育費のうち、通常必要と認められるものは、非課税になります。
基礎控除110万円とは別途、非課税となりますので、有効に使用することで効果があります。
2 婚姻期間20年以上の夫婦の間での居住用不動産等の贈与の配偶者控除(2000万円まで)
婚姻期間20年以上の夫婦で居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭(特定贈与財産)の贈与があった場合、基礎控除110万円とは別途、2000万円の配偶者控除を受けることができます。
また、死亡前3年以内(2024年(令和6年)1月1日以降の贈与では死亡前7年以内)の贈与でも、贈与額を相続財産に加算しません。
ただし、贈与税の申告をすることが必要になりますので、ご注意ください。
3 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税(500万円又は1000万円まで)
父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築、取得又は増改築の資金の贈与について、一定の要件を満たす場合、基礎控除110万円とは別途、500万円(省エネ等住宅の場合、1000万円)の控除を受けることができます。
なお、一定の場合とは、受贈者が18歳以上であること、所得が2000万円以下(床面積が40㎡以上50㎡未満では1000万円以下)であること、贈与の翌年3月15日までに取得し、原則居住することなどである。
対象となる住宅の要件は、2分の1以上が居住用であること、国内にあること、床面積が40㎡以上240㎡以下であること、耐震性がある又は昭和57年(1982年)1月1日以降に建築されたことなどである。
4 教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税(1500万円まで)
父母(祖父母)が金融機関の子(孫)(0歳から29歳までで、所得1000万円以下)名義の専用口座に教育資金を拠出した場合、1500万円までが非課税となります。
この非課税の適用を受けるためには、教育資金管理契約締結時に、「教育資金非課税申告書」を金融機関などを通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。
また、金融機関などから金銭の払戻し及び教育資金の支払を行った場合、教育資金の支払に充てた領収書などを金融機関などに提出する必要があります。
なお、教育資金管理契約期間中に教育資金の贈与者が死亡した場合、相続税の申告が必要となる場合があります。
また、孫などが30歳に達したことなどにより教育資金管理契約が終了した場合、贈与税の申告が必要となる場合があります。
5 結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税(1000万円まで)
父母(祖父母)が金融機関の子(孫)(18歳から49歳までで、所得1000万円以下)名義の専用口座に結婚・子育て資金を一括して拠出した場合、1000万円までが非課税となります。
この非課税の適用を受けるためには、結婚・子育て資金管理契約締結時に、「結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関などを通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。
また、金融機関などから金銭の払戻し及び育結婚・子育て資金の支払を行った場合、結婚・子育て資金の支払に充てた領収書などを金融機関などに提出する必要があります。
なお、結婚・子育て資金管理契約期間中に教育資金の贈与者が死亡した場合、相続税の申告が必要となる場合があります。
また、子などが50歳に達したことなどにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合、贈与税の申告が必要となる場合があります。
生前贈与の活用例
1 暦年課税のメリット・デメリット
暦年課税制度のメリットは、➀3年間(2024年(令和6年)1月1日以後の贈与では7年間)の経過により相続税と切り離され、相続税法第49条の開示対象外になること、➁贈与対象者は推定相続人に限られず、多くの者を対象とすることができること、➂推定相続人については➀の3年(7年)の期間を考慮する必要がないこと、➃受贈者が未成年でも適用できること、➄直系尊属から18歳以上の者が贈与を受ける場合、特例税率となり優遇されることなどです。
暦年課税制度のデメリットは、➀基礎控除が110万円しかないため、多額の贈与はできないこと、➁累進税率の税率が高いことなどです。
2 相続時精算課税制度のメリット・デメリット
相続時精算課税制度のメリットは、➀2500万円まで非課税となり、一度に多額の贈与を行うことができること、➁2024年(令和6年)1月1日以後の贈与では、基礎控除110万円が認められること、➂相続時の加算額は贈与税の課税価額であるため、将来価値が上昇する財産を贈与することが有効であることなどです。
相続時精算課税制度のデメリットは、➀一度相続時精算課税制度祖選択すると、その贈与者からの贈与については、暦年課税を選択することはできないこと、➁贈与時より贈与した財産の価値が下落しても相続税は下がらないこと、➂受贈者が贈与者より先に死亡すると二重課税になるおそれがあること、➃不動産の贈与の場合、登録免許税の税率が0.4%から2%まで上昇し、不動産取得税もかかること、➄相続税法第49条の開示の対象となることなどです。
3 相続財産が1億円の場合における生前贈与の活用案
1 生前贈与などの対策をしない場合
例えば、相続財産が1億円で法定相続人が配偶者、子2人のケースで、生前贈与などの対策を全くしなかった場合、法定相続に従って遺産分割をすると、相続税は以下のとおり、315万円になります。
・ 課税対象額:5200万円=1億円-4800万円(基礎控除、3000万円+600万円×3人(法定相続人の人数))
・ 算出税額 : 630万円=340万円(配偶者分)+145万円(子分)+145万円(子分)
・ 配偶者 : 340万円=5200万円×1/2×15%ー50万円
・ 子 : 145万円=5200万円×1/4×15%ー50万円
・ 納付税額 : 315万円=630万円ー315万円(配偶者の軽減額)
2 相続まで5年間で対策する場合
例えば、上記のケースで、➀子2人には1年目は110万円ずつの暦年贈与を行って、2年目から相続時精算課税制度で110万円ずつの贈与を行う、➁配偶者には2年間、110万円ずつの暦年贈与を行う、➂子の配偶者及び孫4人に対して5年間毎年、110万円ずつの暦年贈与を行うという生前贈与を実行したとします。
この場合、配偶者、子、子の配偶者及び孫4人の受けた贈与財産の合計額は、以下のとおりです。
・ 配偶者: 220万円=110万円×2年
・ 子 :1100万円=110万円×5年×2人
・ 子の配偶者及び孫4人:3300万円=110万円×5年×6人
・ 合 計:4620万円
そして、相続税は以下のとおり、29万5000円となり、285万5000円の節税になります。
・ 課税対象額: 590万円=1億円-4620万円-4800万円(基礎控除、3000万円+600万円×3人(法定相続人の人数))+10万円(配偶者の生前贈与加算)
・ 算出税額 : 59万円=29万5000円(配偶者分)+14万7500円(子分)+14万7500円(子分)
・ 配偶者 :29.5万円 =590万円×1/2×10%
・ 子 :14.75万円=590万円×1/4×10%
・ 納付税額 : 29.5万円=59万円ー29.5万円(配偶者の軽減額)
3 相続まで10年間で対策する場合
例えば、上記のケースで、➀子2人には3年間は110万円ずつの暦年贈与を行って、4年目から相続時精算課税制度で110万円ずつの贈与を行う、➁配偶者には4年間、110万円ずつの暦年贈与を行う、➂子の配偶者及び孫4人に対して10年間毎年、110万円ずつの暦年贈与を行うという生前贈与を実行したとします。
この場合、配偶者、子、子の配偶者及び孫4人の受けた贈与財産の合計額は、以下のとおりです。
・ 配偶者: 440万円=110万円×4年
・ 子 :2200万円=110万円×10年×2人
・ 子の配偶者及び孫4人:6600万円=110万円×10年×6人
・ 合 計:9240万円
そして、相続税は以下のとおり、0円となり、315万円の節税になります。
・ 課税対象額: 0円=1億円-9240万円-4800万円(基礎控除、3000万円+600万円×3人(法定相続人の人数))+10万円(配偶者の生前贈与加算)
・ 納付税額 : 0円
贈与財産か名義財産かの事実認定の問題
1 名義財産とは
名義財産とは、名義は相続人・他の親族などであっても、実質的には被相続人の財産であると考えられる財産(預貯金・株式など)をいいます。
名義財産のうち、預貯金を名義預貯金、株式を名義株式などともいいます。
実務上、相続税の税務調査などにおいては、贈与財産か名義財産かについて、事実認定の問題が生じることが良くあります。
2 名義預貯金の判断基準
例えば、名義預貯金では、預貯金通帳、預貯金証書の管理、定期預金の書換え・解約・新規設定等の手続などを行っていたのかが誰か、金融機関の届出印は被相続人と受贈者などで同じかどうか、預貯金の贈与などを受けていることの認識が受贈者などにあるかどうか、贈与税の申告をしているかどうかなどが判断基準となります。
預貯金の管理などを被相続人が行っていた場合、名義人が預貯金を知らなかった場合などは、名義預貯金と判断される可能性が高いと考えられます。
生前贈与契約書作成を依頼した場合の弁護士費用
※公正証書遺言の作成には、公証人役場所定の公証人報酬及び立会人2名分の日当が必要になります。
※相続財産調査・相続人調査が必要となる場合、別途費用をいただくことがあります。
遺言書作成を依頼した場合の弁護士費用
※公正証書遺言の作成には、公証人役場所定の公証人報酬及び立会人2名分の日当が必要になります。
※相続財産調査・相続人調査が必要となる場合、別途費用をいただくことがあります。
※遺言書作成状況の報告書作成、録音及び録画に関しては、別途費用をいただくことがあります。
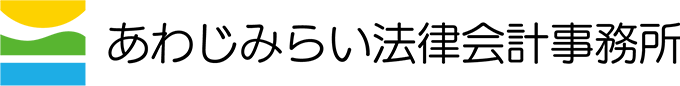
 24時間365日受付
24時間365日受付