「許容される節税策と行き過ぎた節税策の区別」(ひょうご宅建広報『ひょうご宅建プレス』2023年7月号寄稿)
企業法務Contents
-許容される節税策と行き過ぎた節税策の区別-
マンションの相続税評価額について市場での売買価格と財産評価基本通達評価額とに大きな乖離が生じている実態を利用したいわゆるタワマン節税スキームに関して、税務当局による不動産鑑定評価額をもとにした更正処分等を適法なものと認め、納税者敗訴とした事例(最高裁令和4年4月19日判決)
1 はじめに
本稿では、財産評価基本通達評価額によって不動産評価をした相続税の申告に対して札幌南税務署長(以下「処分行政庁」といいます。)が行った不動産鑑定評価額に基づく更正処分等(以下「本件処分」といいます。)について判示した2022年4月19日付最高裁判決(最判令和4年4月19日民集第76巻4号411頁)(以下「本件判決」といいます。)を紹介します。
本件判決では、本件処分を適法とし判断し、納税者敗訴となった1審・控訴審の判断を妥当なものと判示しました。
マンションの相続税評価額については、市場での売買価格と財産評価基本通達評価額とに大きな乖離が生じている実態を利用したいわゆるタワマン節税スキーム等が存在している現状に対して、2024年(令和6年)以降の税制改正を見据えて、現在、マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議が開催されています。
本件判決は、こうした市場での売買価格と財産評価基本通達評価額との乖離を利用した富裕層による相続税対策に関して、最高裁が納税者側敗訴の判断を認めたものであり、相続税申告実務にとどまらず相続に関連した不動産取引自体にも大きな影響を及ぼすものと考えられます。
2 事案の概要
⑴ 被相続人A(大正7年(1918年)生、平成24年(2012年)没)は、相続開始前の平成21年(2009年)1月(当時90歳)、6億3000万円を借り入れた上で、8億3700万円の建物(共同住宅・店舗)(以下「本件建物」といいます。)を購入しました。
また、被相続人Aは、相続開始前の平成21年(2009年)12月(当時91歳)、4億2500万円を借り入れた上で、5億5000万円の土地(宅地)(以下「本件土地」といいます。)を購入しました。
なお、借り入れに際して作成された貸出稟議書の理由欄には、「相続(税)対策」等の記載がありました。
⑵ 平成24年(2012年)6月、被相続人Aは死亡し、相続が開始しました。
なお、本件土地は被相続人の遺言に従って、相続人の一人が取得しましたが、平成25年(2013年)3月、5億1500万円で第三者に売却されました。
平成25年(2013年)3月、相続人らは、財産評価基本通達の定める方法によって本件物を約2億円、本件土地を約1億3400万円と評価し(以下「本件通達評価額」といいます。)、課税価格2826万1000円、相続税の総額0円とする相続税の申告書を提出しました(以下「本件相続申告」といいます。)。
なお、上記⑴の借入及び不動産の購入(以下「本件借入及び購入」といいます。)がなければ、課税価格の合計額は6億円を超えることが見込まれました。
⑶ 平成28年(2016年)4月、札幌南税務署長(処分行政庁)は、不動産鑑定士による鑑定評価額(以下「本件鑑定評価額」といいます。)に基づき、本件建物の評価額が7億5400万円、本件土地の評価額が5億1900万円であることを前提として、課税価格を8億8874万9000円、相続税の総額を2億4049万8600円とする更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件更正処分等」といいます。)をしました。
⑷ このため、平成29年(2017年)11月、相続人らは本件更正処分等の取消を求め、訴訟提起しました(なお、訴え提起前の国税不服審判所に対する審査請求は、棄却されました。)。
令和元年(2019年)8月の第一審判決、令和2年(2020年)6月の2審判決はいずれも相続人ら(納税者ら)敗訴の判決でした。
令和4年(2022年)4月19日、最高裁判所は、次のとおり判断し、相続人らの上告を棄却し、相続人ら(納税者ら)敗訴の1審・2審の判断を妥当なものと判示しました。
3 最高裁判所の判決要旨
⑴ 相続税法22条において、相続財産の評価額は取得時の時価、すなわち、財産の客観的な交換価値であると規定されているのに対して、財産評価基本通達は行政規則である通達に過ぎず、国民に対する直接の法的効力を有しない。
したがって、本件更正処分等に算入された客観的な交換価値としての時価である本件鑑定評価額が、財産評価基本通達評価額を上回ることは、相続税法22条に違反するものではない。
⑵ 特定の者の相続財産の価額についてのみ、財産評価基本通達評価額を上回る価額によることは、合理的な理由がない限り、租税法上の一般原則としての平等原則に違反し、違法である。
⑶ もっとも、次の➀、➁などの事情のもとにおいては、本件通達評価額による課税は、実質的な租税負担の公平に反するという事情があるから、本件鑑定評価額による課税には、合理的な理由があると認められ、本件更正処分等は平等原則に違反しない。
➀ 本件通達評価額(合計3億3400万円)と本件鑑定評価額(12億7300万円)との間には大きな乖離があるところ、本件借入及び購入の結果、相続人ら(納税者ら)の相続税の負担が著しく軽減されていること(本件借入及び購入が行われてなければ課税価格の合計額は6億円を超えるものであったにもかかわらず、本件相続申告の課税価格は2826万1000円にとどまり、相続税の総額が0円であること)。
➁ 本件借入及び購入が租税負担の軽減をも意図して行われたこと(被相続人及び相続人ら(納税者ら)は本件借入及び購入が近い将来発生することが予想された相続における相続税の負担を減じ又は免れさせることを知り、かつ、これを期待して、あえて本件借入及び購入を企画して実行したこと)。
4 判決に対するコメントと実務上の留意点
本件判決では、租税負担の軽減をも意図して行われた借入及び不動産の購入によって、相続税の負担が著しく軽減された場合、不動産鑑定評価額による更正処分等が行われたとしても適法であるという判断がなされました。
これによって、相続税申告実務上では、過度な相続税対策が行われていると判断され得る場合、不動産の評価を財産評価基本通達評価額ではなく、不動産鑑定評価額等により行い、相続税の申告をせざるを得ない場合も生じるものと考えられます。
特に、不動産購入に際して借り入れが行われている場合、不動産の購入時期が相続開始前5年以内である場合、市場での売買価格と財産評価基本通達評価額との間に大きな乖離がある場合、不動産の購入等に相続税対策以外の経済的合理性が認められない場合、相続税の負担が著しく軽減されている場合等では、税務当局による不動産鑑定評価額等による更正処分等が行われるおそれがあるため、上記のような対応を行うことを検討せざるを得ないものと考えられます。
なお、2024年(令和6年)以降の税制改正では、マンションの相続税評価額の引き上げ、相続税評価額の再評価基準の明確化等が行われることが見込まれるため、関係者においては、国税庁において開催・公表されているマンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議の動向にも注目しておく必要があるものと考えられます。
5 執筆者
弁護士 藤井貴之(兵庫県弁護士会所属)
兵庫県加古川市出身。神戸大学法学部卒業、神戸大学法科大学院修了。
2013年弁護士登録。令和2年(2020年)公認会計士試験合格。
弁護士登録後、勤務弁護士・外資系コンサルティングファーム等を経て、弁護士法人ひょうごを開設。
これまで、相続関係事件、損害賠償請求事件(交通事故、労災事故、学校事故等)などの個人の案件、役員責任、労働法務、経営権争奪紛争、企業間取引紛争などの企業・法人の案件を中心としたさまざまな案件に携わる。
公認会計士試験合格後は、財務諸表監査・財務DDなどの公認会計士業務にも従事しており、弁護士資格と公認会計士資格のダブルライセンスを活かし、決算書の絡む企業間の損害賠償請求事件、M&A・事業承継、粉飾・不正調査などにも力を入れている。
-1024x731.jpg)
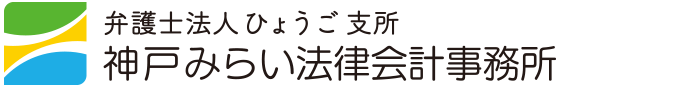
 24時間365日受付
24時間365日受付